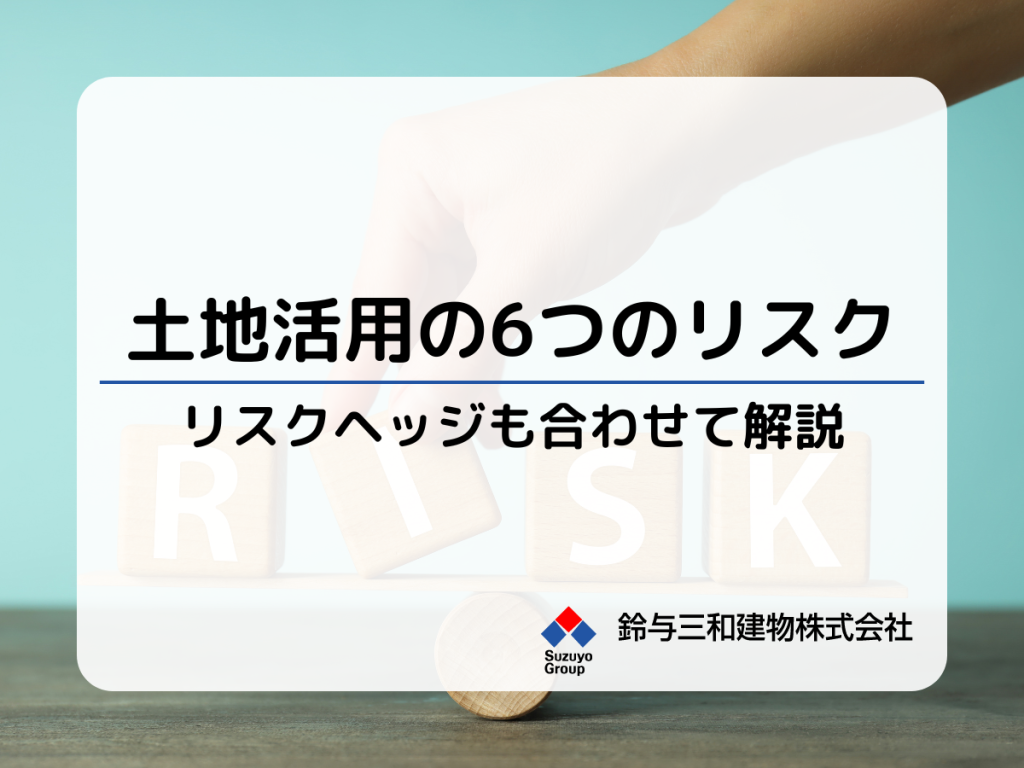気候変動リスクと土地活用設計 ― 災害リスクを前提にした資産価値の守り方と活かし方―
2025.10.21 UP
はじめに:土地活用にも「災害対策」が必要な時代に
近年、日本各地で大規模な自然災害が頻発しています。ゲリラ豪雨による都市部での浸水、台風による高潮被害、そして山間部での土砂災害。
ニュースで「これまでに経験のない規模の災害」と報じられることが増えていますが、残念ながらそれはもはや特別なことではなく、毎年どこかで起きている現実となっています。
背景には、気候変動による影響があります。気温上昇によって大気中の水蒸気量が増え、豪雨が発生しやすくなる。海面上昇や台風の大型化により、沿岸部では高潮や浸水のリスクが高まる。
こうした現象は、今後さらに進むと予測されています。
土地や建物は長期的に利用される資産です。そのため、「今の環境が安全だから大丈夫」という発想では十分ではありません。むしろ、これから起こり得る災害を前提に計画を立てることが必要です。
土地活用の中に「防災」の視点をしっかりと組み込むことは、資産を守るだけでなく、将来的な価値を高める戦略でもあるのです。

ハザードマップで土地のリスクを確認する
土地活用を考える際に、まず確認したいのが「その土地にどんな災害リスクがあるのか」です。
各自治体が公開しているハザードマップを活用すると、洪水や高潮、土砂災害などの危険性を色分けされた地図で確認できます。
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| ・洪水リスク | 川の氾濫やゲリラ豪雨による浸水がどこまで及ぶか |
| ・高潮リスク | 海に面した地域で高波や潮位上昇により浸水する可能性 |
| ・土砂災害リスク | 急な斜面や山間部で土砂崩れや地滑りが発生する恐れ |
| ・地震リスク | 活断層の位置や地盤の強弱によって、揺れやすさや液状化の危険性が異なる |
地震リスクについては、地盤の強さや地形によって被害の大きさが左右されるため、ハザードマップで「揺れやすさ」や「液状化の可能性」を確認することが大切です。建物の耐震性能を考えるうえでも、事前の情報把握が欠かせません。
マップを見れば、土地が災害危険区域に入っているかどうか、あるいは建築に制限がある区域かどうかが分かります。これを把握しておくことで、被害のリスクを避けた土地活用が可能になります。
たとえば同じエリアであっても、道路を挟んだ向かい側は洪水浸水区域に指定されているのに、自分の土地は安全区域に入っている、といったケースもあります。
こうした情報を知らずに計画を進めると、思わぬリスクを抱えることになりかねません。
ハザードマップはインターネット上でも公開されており、スマートフォンからも簡単に確認できます。土地活用を検討する最初のステップとして必ず押さえておくべきツールです。

保険や公的制度を組み合わせて備える
災害に対する備えは、建物の構造だけでは十分ではありません。
保険や公的制度を組み合わせておくことで、リスクに対する安心感をさらに高めることができます。
まず大切なのが保険です。火災保険や地震保険は広く知られていますが、洪水や土砂崩れによる被害を補償する「水災補償」を付けておくことも重要です。実際に、近年の集中豪雨で大きな浸水被害を受けたエリアでは、水災補償の有無によって被害後の経済的負担に大きな差が出ています。
ただし、リスクの高い地域では補償が限定されたり、保険料が高額になったりするケースもあるため、契約内容を定期的に見直すことが欠かせません。
次に、公的な支援制度です。国や自治体は、耐震補強や排水設備の導入、防災関連工事に対して補助金や助成金を用意しています。これらをうまく活用すれば、初期投資を抑えながら災害対策を進めることが可能です。たとえば「浸水対策の排水ポンプ設置」や「老朽化した建物の耐震補強」などが補助対象になるケースがあります。こうした支援制度は年度ごとに内容が変わることも多いため、最新情報を把握しておくことが重要です。
「建物を建てること」だけに集中するのではなく、保険や制度を含めて多層的に備えることで、万一の事態においても資産を守る力が強まります。
災害に備えることが資産価値を守る
「防災対策」というと、つい「コスト」や「負担」として捉えがちです。しかし実際には、災害に備えることがそのまま将来の資産価値を守る手段にもなります。
まず、災害に強い建物は入居者から選ばれやすくなります。大雨や台風が頻発する中で、「安心して暮らせるかどうか」は住まい選びの大きなポイントです。防災対策のある物件は空室リスクが減り、安定した賃貸経営につながります。
さらに、売却時や融資を受ける際にも、防災性の高い不動産は評価が上がる傾向があります。金融機関もリスクを重視しており、災害リスクが低い物件は資産価値が下がりにくいと見なされます。
近年では「ESG投資(環境・社会・ガバナンス)」や「レジリエンス(回復力)」といった考え方が広がっており、災害に強い不動産は社会的な評価も高まりやすいのです。
つまり、防災への取り組みは単なる備えではなく、未来の資産価値を押し上げる投資でもあります。

まとめ
これからの土地活用を考える上で、気候変動による洪水や土砂災害といったリスクを無視することはできません。むしろ、それらを前提にした計画こそが、資産を守り、将来の価値を高めることにつながります。ご所有地の災害リスクを事前に調べたうえで、建物の設計段階から「水害に強い工夫」や「安全性を高める設備」を取り入れることで、長期的に安心して活用でき、安定した経営を実現することが可能となります。
また、こうした取り組みを効果的に進めるためには、専門的な知識を持つパートナーと連携することが不可欠です。安心・安全であり、さらに将来も高く評価される土地活用を実現するためには、この視点が今後の必須条件になるといえるでしょう。
鈴与三和建物では、お客様の土地の特性やリスクを踏まえたうえで、最適な活用方法をご提案しています。資産を「守りながら活かす」ための土地活用をお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。