【土地活用の最新事情】RC構造の建築費が高騰する5つの理由|資材・人件費・円安・金融の影響とは?
2025.10.28 UP
Contents
- ──物価上昇の裏に潜む「構造的メカニズム」を読み解く──
- ■1. 土地活用でRC構造が高騰してもなお選ばれる理由
- ■2.建築資材高騰が土地活用コストに及ぼす影響|グローバル経済と国内需給の二重圧力
- ■3. 職人不足が土地活用の採算を圧迫する理由|「人」が最大のボトルネックに
- ■4. 都市集中と再開発 | 大規模プロジェクトが中小案件を圧迫
- ■5. 円安がRC建築コストを直撃するメカニズム | 為替が建築費を押し上げる新要因
- ■6. 金融政策と市況の関係 | “低金利の副作用”が建設需要を刺激
- ■7. 建築費高騰時代の土地活用成功戦略とコスト最適化のポイント | 「高い」をどう乗り越えるか
- ■ 結論:高騰の正体は「構造的な必然」
- 関連コラム
──物価上昇の裏に潜む「構造的メカニズム」を読み解く──
いま、RC構造の建築費が以前に比べて異常値になっており、土地活用を検討している方の多くが直面しているのが「建築費の高騰」です。
ここ数年、土地活用を検討するオーナーの間で最もよく聞かれる言葉が「建築費が上がった」です。
特に、都市部で主流の鉄筋コンクリート(RC)構造は、耐久性・防火性・遮音性といった優れた性能を持つ一方で、建築コストがかつてない水準に達しています。
RC構造の建築費は2015年頃と比べて約25〜35%上昇しており、同じ規模・仕様の建物でも見積額が大きく変わる時代になりました。この現象を「物価高騰の一言で済ませる」ケースもありますが、実際にはその裏に複数の経済的・構造的要因が複雑に絡み合っているのです。
本稿では、RC建築費の上昇要因メカニズムを「資材」「人」「都市構造」「金融」「円安」の5つの視点から分解し、土地活用を成功させるための実践策を紹介します。
■1. 土地活用でRC構造が高騰してもなお選ばれる理由
RC構造(鉄筋コンクリート造)は、長期的な資産価値・耐震性・遮音性能に優れ、都市型マンションや賃貸ビルの定番構造です。
特に東京23区のような防火地域・準防火地域では、RC構造でないと法規的に建築できないケースも多く、需要が集中します。
また、税務上の耐用年数47年という長さも魅力です。減価償却期間が長く、資産としての安定性が高いため、投資志向のオーナーに支持されています。
その一方で、RC構造は木造や鉄骨造に比べて工期が長く、職人の手間が多いため、社会的変化がコストに直結しやすいという弱点も抱えています。


■2.建築資材高騰が土地活用コストに及ぼす影響|グローバル経済と国内需給の二重圧力
RC構造の建築費高騰の第一の要因は、基幹資材の上昇です。特に鉄筋・セメント・生コンクリートは、国際市況と国内需給の両面から上昇圧力を受けています。
●鉄筋価格の背景
近年、中国やインドなど新興国の建設需要拡大により、世界的に鉄鋼需要が高止まりしています。
日本国内では電炉メーカーが電気代・原料コストの上昇に直面し、製造単価を引き上げざるを得ない状況です。
●コンクリート供給のひっ迫
コンクリートは一見「国内生産品」ですが、実は原料の骨材(砂・砕石)の採掘量が年々減少。
加えて、輸送ドライバーの不足と労働時間規制(2024年問題)によって物流コストが上昇しています。
都市部の工事現場では、生コンプラントの稼働時間制限も影響し、供給制限=単価上昇という構図が常態化しています。
■3. 職人不足が土地活用の採算を圧迫する理由|「人」が最大のボトルネックに
資材よりも深刻なのが職人の不足です。
RC工事は、型枠大工・鉄筋工・左官・コンクリート打設など、多数の専門職が関与します。
ところが、これらの職種は技能者の高齢化が進み、若手の参入が減少しています。
令和4年度国土交通省の統計によると、建設業就業者479万人の内、55歳以上が約35.9%、29歳以下に関しては11.7%で若手育成が追いつかないまま退職者が増え、業界全体で「人の奪い合い」が発生しています。
その結果、現場では職人の日当が上昇し、労務費が建築費の3〜4割を占める構造になっています。
この「人材コストの固定的上昇」は、物価下落局面でも戻りにくく、RC構造の高コスト化を慢性化させる要因になっています。
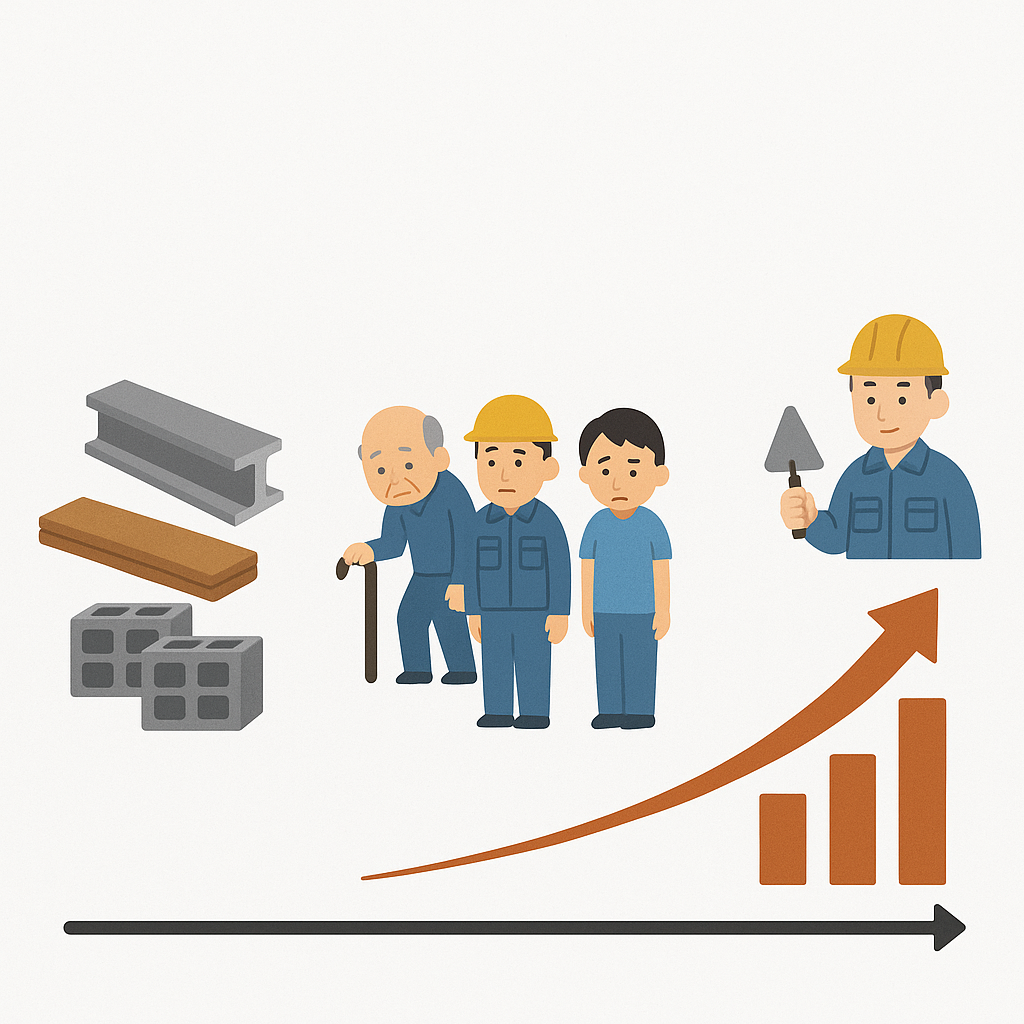

■4. 都市集中と再開発 | 大規模プロジェクトが中小案件を圧迫
東京や大阪などの都市圏では、再開発・インフラ更新・大型マンション計画が同時多発的に進行しています。
この都市集中現象が、中小規模の土地活用案件にしわ寄せを生んでいます。ゼネコンや下請け業者は大手案件を優先するため、小規模RCマンションなどでは「職人確保ができない」「着工が遅れる」「見積りが跳ね上がる」といった問題が相次いでいます。
つまり、建築費高騰は単なる“資材の値上がり”ではなく、業界全体のリソース配分が偏ることによる構造的現象でもあります。
■5. 円安がRC建築コストを直撃するメカニズム | 為替が建築費を押し上げる新要因
ここ数年の急速な円安も、建築費上昇の新たな引き金となっています。
鉄筋・銅線・機械設備など、RC建築に欠かせない多くの素材や部品は海外からの輸入依存度が高いため、為替変動が直接価格に反映されます。
円安が進むと、輸入材料費だけでなく、燃料・物流・重機リース料といった周辺コストにも波及。また、外資系建設資材メーカーの価格交渉力が強まり、国内業者が値下げに応じにくくなる傾向も見られます。
為替レートの変化は短期間でも影響が大きく、「1ドル=10円の差」で総工費が数%変動するケースもあり、今後の土地活用計画では無視できないリスク要因です。
2025年9月平均で1ドル147.93円に対し2020年9月平均は105.79円と5年で約40%の円安ドル高となっております。
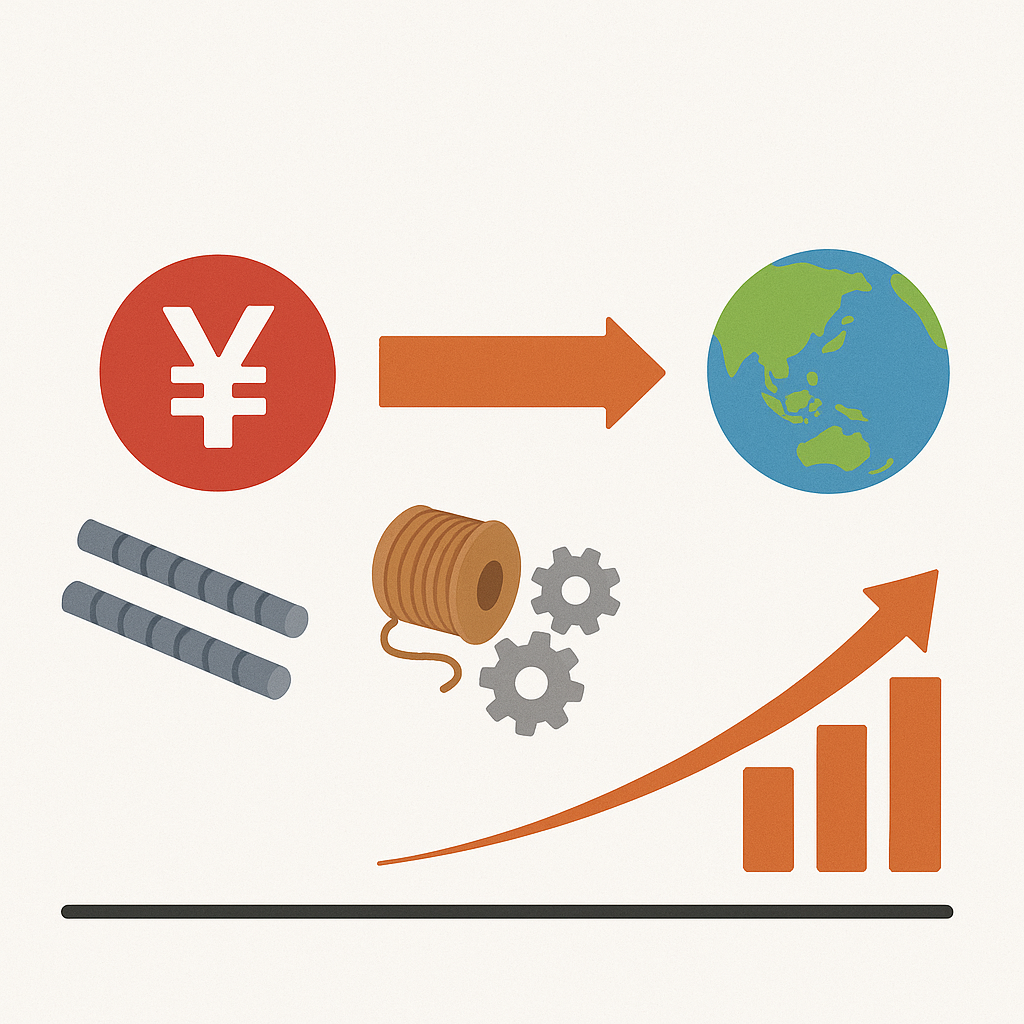

■6. 金融政策と市況の関係 | “低金利の副作用”が建設需要を刺激
一見関係がないように見えるのが金融政策ですが、実はこれも大きな要因です。
長期にわたる超低金利政策により、不動産投資や再開発が全国的に活発化。
企業や投資家が資金調達しやすくなった結果、建設需要が常に高水準で維持されてきました。
需要過多の状態が長引くことで、資材や人件費の高止まりを招いているのです。
この「好況の裏のコスト上昇」は、土地活用を行う中小事業者にも波及しています。
■7. 建築費高騰時代の土地活用成功戦略とコスト最適化のポイント | 「高い」をどう乗り越えるか
建築費が高騰している今こそ、「建てない」という選択ではなく、「どう建てるか」を考える時期です。土地活用を長期的に成功させるためには、初期費用だけでなく、運用・修繕・利回りを見据えた戦略が求められます。
●発注時期の見極め
資材市況が落ち着くタイミングを狙い、早期契約・段階発注を行うことで価格変動リスクを軽減できます。
●長期収支での判断
RCは耐用年数が長く、修繕頻度も少ないため、長期運用では利回りの安定度が高いという強みがあります。「初期コスト」ではなく「生涯コスト」での収支設計が重要です。
●施工会社の選定 ― 発注方式でコストを最適化する
建築費が高騰する中では、発注方式の選び方がコストに直結します。
大手ゼネコンへの一括発注は品質・工程の安定性が高い一方で、下請け構造や間接費が多くコスト上昇リスクがあります。
その点、地域密着型の施工会社は現場対応が早く、仕様変更にも柔軟。さらに、自社で設計から施工まで行う直営施工方式を採用する企業であれば、中間マージンを抑えつつ意思決定をスピーディーに行えるのが利点です。
また、案件規模によっては分離発注方式(各工事を直接契約)も有効です。ゼネコンを介さない分コストを抑えられますが、発注者側に一定の知識と管理体制が求められます。
つまり、一括発注・直営施工・分離発注のどれを選ぶかで、同じRC構造でも総工費が数%〜10%変わることもあります。
コスト・品質・管理のバランスを見極めた施工会社選定が、土地活用成功の鍵です。
■ 結論:高騰の正体は「構造的な必然」
RC構造の建築費高騰は、単なる「物価高騰」ではありません。
それは、資材・人材・都市構造・金融・円安という5つの要素が複雑に絡み合った経済構造的な必然です。
短期的な価格変動に一喜一憂するのではなく、この構造を理解した上で長期収益性と資産価値の両立を図ることが、土地活用における最も現実的な戦略といえるでしょう。
「価格は時代の鏡。為替も構造も読む力が、土地活用の成功を左右する。」

私たち鈴与三和建物株式会社は創業以来90年間、お客様の不動産に関するお悩みやご検討事を解決するお手伝いをしてきました。
その中で培った経験やノウハウを基に、お客様のご所有する不動産の現状把握等、調査やコンサルティング業務も行っております。
お悩みがある方は是非お気軽にお問合せくださいませ。

